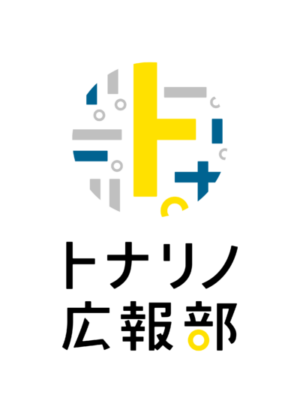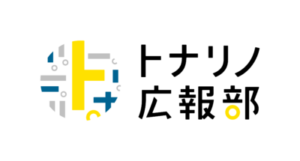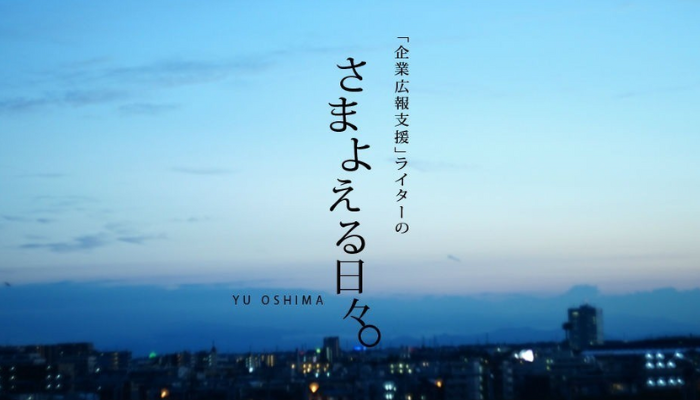このコラムは、あるひとりのライターが「企業広報支援ライター」と名乗って活動していた5年間(2013年〜2018年)の経験をもとに書いた当時のブログを、一部改訂して再掲したものですわたしはかつて、「企業広報支援ライター」と名乗っていた。当時、だいたいの人は、名刺をわたすと一度首をかしげて「ちょっと説明してくれる?」という目でわたしを見てくることが多かった。要するにいろいろな広報ツールやテキストコンテンツを作ることを生業としていたわけなのだが、どうやらライターとしてはずいぶんニッチなジャンルだったらしい。正直、じぶんがフリーランスになるまで、そんなことぜんぜん思って