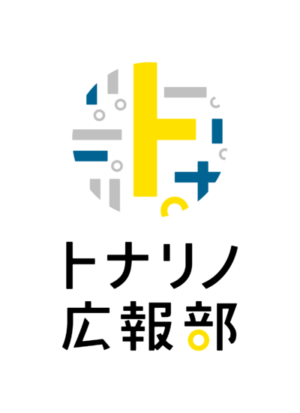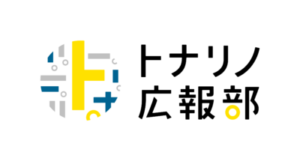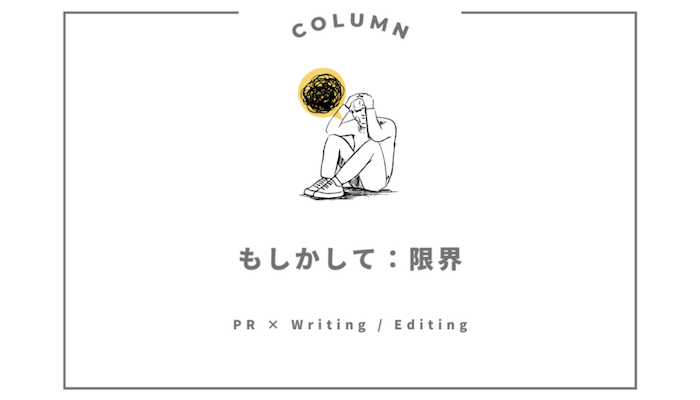なんだか、ものすごく分断やすれ違いが増えてない?――そんな風に感じることが、ここのところとても増えました。だからこそメンバーのみなさんともこの感覚を、一度共有しておきたいなと思います。(Slackにてぜひご意見お寄せください!)トナリノ広報部というコミュニティは「PR/広報領域で活動するライター・編集者のコミュニティ」としてはじまり、「書く力を、企業(ビジネス)にどう役立てる?」を共通の合言葉として活動してきました。たださまざまな分断やすれ違いを経験し、自分たちの仕事について「PR」「広報」「ライター(ライティング)」「編集者(編集)」あたりの言葉を用いて表現することに、そろそ